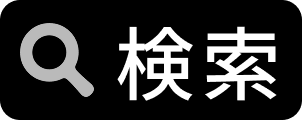シニョリッジとは、通貨を発行することによって得られる利益を指します。具体的には、貨幣や紙幣の額面価値から製造コストを差し引いた差額で、政府や中央銀行が得る収益のことです。
1. 基本概念と意味
- 通貨発行益:製造コストが低い通貨(例:1万円券)を発行することで得る差益がシニョリッジです。
- 経済的には税金のような性質:現物の価値を劣化させるインフレによって、実質的に資産が移転される「インフレーション税」と見ることもあります。
2. 仮想通貨における応用と意味
- 伝統的フォーマットと類似:アルゴリズム型ステーブルコインでは、需要と供給に応じて供給量を調整し、価格を維持する仕組みを「シニョリッジモデル」と呼びます。
- 発行体の潜在的利益構造:トークンの価値が上昇すると、初期発行時点で保有した分の「含み益」が増加し、発行体や初期関係者に経済的利益をもたらします。これもシニョリッジ的な収益と捉えられます。
3. 古典的なシニョリッジと現代経済
- 歴史的背景:シニョリッジの語源は封建領主の特権(seigneur)にあり、元々は貨幣鋳造に伴う主権者の利益を意味していました。
- 現代における利用:中銀は紙幣や電子マネーの発行によって、製造コストとの差額として利益を得ています。
4. 利点とリスク・批判
利点
- 政府や中央銀行の強力な財源:税金をかけずして支出財源を確保可能。
- ステーブルコインなどのアルゴリズムモデル:市場操作や外部資産なしで価値安定の仕組みを形成可能。
リスク・批判
- インフレ誘発リスク:過度の通貨発行は通貨価値を希薄化し、インフレにつながる可能性。
- 分配の不公平:中央銀行やマイナーなど一部主体に利益が偏る可能性がある。
まとめ
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 概念 | 額面価値 − 製造コスト=通貨発行益 |
| 古典的用途 | 国家・中央銀行の収益源 |
| 仮想通貨への転用 | アルゴ式ステーブルコインモデルやトークン発行の含み益 |
| 重要性 | インフレ・資産循環・プラットフォーム設計の基礎理論 |
シニョリッジは、伝統的な通貨発行の仕組みと同様に、仮想通貨やステーブルコインの設計においても重要な概念です。価格安定・供給調整・利益構造を理解する上で不可欠な考え方です。