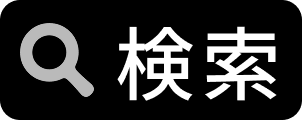1. 概要
セグウィット(Segregated Witness / SegWit)とは、ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するために導入されたソフトフォークによるアップグレードです。2017年8月にビットコインのネットワークに実装され、トランザクションデータの構造を最適化することで、ブロックサイズの有効活用や手数料の削減、トランザクション速度の向上を実現しました。
セグウィットは、トランザクションの署名データ(Witness)を分離し、ブロックのメインデータとは別に格納することで、1ブロックあたりに格納できる取引数を増やす仕組みです。
2. セグウィットの主な特徴
(1) スケーラビリティの向上
- 署名データを分離することで、1MBのブロックサイズ制限の有効活用が可能。
- 取引データの圧縮により、1ブロックあたりに処理できるトランザクション数が増加。
(2) 取引手数料の削減
- 取引データのサイズが小さくなるため、手数料(ガス代)が低減。
- ユーザーがより効率的に送金を行えるように。
(3) トランザクション展性の解決
- 以前は、送金時にトランザクションID(TXID)が変更される可能性があり、二重支払いなどのリスクがあった。
- セグウィットにより、署名データを分離することで、トランザクションIDの改ざんリスクが軽減。
(4) ライトニングネットワーク(LN)の基盤強化
- セグウィットは、オフチェーン取引(Layer 2ソリューション)であるライトニングネットワーク(LN)の実装を容易にする。
- LNによって、ビットコインの少額決済や即時決済の実用化が進む。
3. セグウィットの仕組み
- ビットコインの通常トランザクションは、入力(インプット)、出力(アウトプット)、署名データの3つで構成されている。
- セグウィット導入前は、署名データ(Witness)がトランザクションサイズの大部分を占めていた。
- セグウィットは、この署名データをメインブロックの外に分離し、ブロックサイズの有効活用を実現。
(1) 通常のトランザクションの構造(SegWit導入前)
[トランザクションID] → [入力] + [署名データ] + [出力](2) セグウィット導入後のトランザクション構造
[トランザクションID] → [入力] + [出力] + [署名データ(分離)]4. セグウィット導入の影響
(1) ビットコインネットワークの改善
- スケーラビリティ問題の部分的な解決。
- 取引手数料の削減。
- 取引のスピード向上。
(2) ビットコインキャッシュ(BCH)の分岐
- セグウィット導入に反対した一部のコミュニティが、2017年8月に**ビットコインキャッシュ(BCH)**としてハードフォーク。
- BCHは、ブロックサイズの拡張(8MB)によるスケーラビリティ解決を目指した。
(3) 取引所・ウォレットの対応状況
- 主要な取引所やウォレット(Exodus、Electrum、Ledger、Trezorなど)はセグウィット対応済み。
- ただし、一部の取引所では従来型のアドレス(Legacyアドレス)を継続して利用しているケースもある。
5. 代表的なセグウィット対応の技術
| 技術 | 内容 |
|---|---|
| Bech32(セグウィットアドレス) | セグウィット対応の新しいアドレスフォーマット(bc1で始まる)。手数料が安く、効率的。 |
| ライトニングネットワーク(LN) | ビットコインのスケーラビリティを向上させるオフチェーン取引技術。 |
| Taproot(タップルート) | セグウィットの発展形で、プライバシーとスクリプトの効率化を向上。 |
6. まとめ
- セグウィットは、ビットコインのスケーラビリティを向上させるソフトフォーク技術。
- 署名データを分離することで、トランザクションのサイズを削減し、ブロック内の取引数を増加させる。
- 取引手数料の削減、トランザクション展性の改善、ライトニングネットワークの基盤強化に貢献。
- ビットコインキャッシュ(BCH)の分岐を引き起こした技術的要因の一つ。
- 主要な取引所やウォレットが対応し、今後のビットコインの発展に寄与する重要な技術。
セグウィットの導入により、ビットコインの利便性と拡張性が向上し、今後の発展にも大きく寄与することが期待されています。