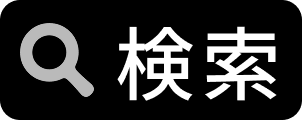学会DAOとは、学術団体(学会)をDAO(分散型自律組織)として構築した組織を指します。ブロックチェーン技術を利用し、従来の中央集権的な運営ではなく、研究者や会員がトークンや投票によって自律的に運営・意思決定を行う新しい形の学会です。
1. 目的とメリット
- ガバナンスの民主化
トークン保有者による議案提案と投票が可能で、意思決定の透明性・公平性が向上します。ウィキペディア+5ddhr.jp+5note(ノート)+5 - 運営コストと手続きの効率化
会費の自動収集、議案可決と予算執行の連動など、スマートコントラクトで運営業務を自動化します。 - 参加と連携の拡大
国内外の研究者がオンラインで参加・貢献しやすくなり、グローバルな共同研究や資金調達が可能に。
2. 仕組みとフロー
- トークン設計と配布
学会トークンを発行し、会員に配布。ステークや貢献度に応じた割当もあり得ます。 - 議案提案と投票
会員が議案を提案し、賛成多数の可決で実行。他のスマートコントラクト(予算支出・イベント承認等)とも連携します。 - 資金管理
会費や助成金がDAOウォレットに集約され、支出は投票を通じて自動執行。透明性が担保されます。
3. 実際の取り組み
- デジタル人材育成学会(DDHR)
2023年に日本初の学会DAOを立ち上げ。提案・投票・資金管理の全工程をブロックチェーン上で行う実証。今後、論文レビュー・研究助成などにもDAO連動を計画中です。note(ノート)+3ddhr.jp+3ddhr.jp+3 - Japan DAO Association(JDA)
PolygonやDfinity上でDAOコミュニティを形成し、AIやブロックチェーン領域の学習・マッチングを支援。学術活動と実務の接続を図ります。Japan DAO Association
4. 課題と今後の展望
- 法制度との整合性
学会登録、論文認定など、既存の制度との整合性をどう担保するかが問われます。 - 技術運用とセキュリティ
スマートコントラクトの脆弱性や投票デザインの公平性に関する設計が重要です。 - 文化・慣習の変革
既存の運営主体(大学、学会幹部など)の理解と参加が必要。既存制度との橋渡しが求められます。
まとめ
学会DAOは、学術団体の意思決定と資金運営を透明かつ民主的に行うブロックチェーン組織です。
研究助成、学術イベント、レビュー制度など幅広い学会行事にDAO技術を適用する可能性があり、グローバルな知識共有と新しい学術運営の形として注目されています。
今後の展開としては、学術的信頼性の担保と制度適合性の確保が鍵となり、各国の学術機関や政府機関との連携が進むことで、学会DAOの社会実装が加速するでしょう。